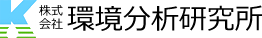季節を彩る花ごよみ
季節を彩る花ごよみ(その11)…ウメ
元号「令和」にも関連が深い日本人好みの花
春を告げる縁起物の花として日本人に親しまれてきたウメ。見た目の愛らしさだけでなく、上品な香りもまた好まれる理由の一つと言えるでしょう。良い香りが漂う様子を表した「馥郁(ふくいく)たる」という言葉は、ウメの香りにこそふさわしいような気がします。
ウメはバラ科・サクラ属の植物。奈良時代以前に遣隋使、あるいは遣唐使が中国から薬木として持ち帰ったと言われています。
開花期は1月~3月頃。白、紅、ピンク色、複色など、花の色は様々です。江戸時代に品種改良が盛んにおこなわれたことから、その種類は300以上もあるのだとか。
花言葉は「上品」「高潔」「忍耐」など凛とした佇まいを感じさせるものが多く、「優美(紅梅)」、「気品(白梅)」と色別に付けられているものもあります。
ウメ全体の花言葉の1つに「忠実」がありますが、これは太宰府へ左遷された菅原道真を追って、庭のウメの木が太宰府へ飛び、根を下ろしたという“飛梅伝説”に由来するもの。道真が京を出る時に庭のウメの前で詠んだ歌「東風吹かば にほひおこせよ 梅の花 あるじなしとて 春な忘れそ」は、あまりにも有名です。
ところで「令和」の元号が発表された時のことを覚えていらっしゃいますか?
この元号の出典は、日本最古の歌集「万葉集」の中の「梅花の歌 三十二首の序文」です。
奈良時代の初めに大伴旅人の邸宅で開かれた「梅花の宴」において、32人が梅の花を題材に歌を詠みました。それらを旅人がまとめた序文として「初春の令月にして 気淑(きよ)く風和らぎ 梅は鏡前の粉を披(ひら)き 蘭は珮後(はいご)の香を薫らす」と記されています。
この中の「令月」と「風和らぎ」から「令和」の元号が生まれました。
新しい元号に奈良時代のウメが深く関わっていたことを思うと、感慨深いものがありますね。
ちなみに、果実収穫の目的で育てられるウメは「実ウメ」と呼ばれます。これには「南高」「白加賀」「豊後」「甲州最小」などの品種があり、もちろん花の観賞も楽しむことができます。
雅な香りとたおやかな存在感を放つ早春花
ウメは身近な場所で気軽に楽しむことができる花木ですが、梅林などの名所も数多くあります。今回は県内でウメの木をたくさん楽しめる場所をご紹介しましょう。
郡山市の西田町は「梅の里」として知られています。4kmにもおよぶ“梅ロード”があり、残雪の安達太良山を背景に約3,000本が咲き誇ります。白梅を中心に、紅梅、レンギョウ、シダレザクラなど色とりどりの風景が見られるのは西田町ならでは。花の見頃は3月下旬~4月上旬とやや遅めです。
またいわき市には、ウメの名所で知られるお寺がいくつかあります。
浄土宗の古刹「専称寺」は境内に約500本のウメが植栽されており、歴史ある建築物と共に美しい景色を織りなしています。見頃は3月中旬。
JR湯本駅に近い「梅林寺」は、名前の通り境内に梅林が広がる名刹。約120本の紅梅・白梅を観賞できます。見頃は2月下旬~3月上旬。
国宝「白水阿弥陀堂」の散策もおすすめ。浄土庭園周辺に咲く紅梅・白梅を眺めながら、平安時代に想いを馳せてみてはいかがでしょう。見頃は2月下旬~3月です。

最後に、当社では下記の検査を行っておりますので、何なりとご用命ください。
●戸建住宅などの水道水水質検査 詳しくはこちらから
●共同住宅や店舗、学校などの建築物飲料水検査や食品営業水質検査 詳しくはこちらから
●井戸水の飲用井戸水検査 詳しくはこちらから