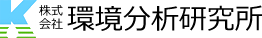ふくしま食紀行
ふくしま食紀行(その3)…ホッキ貝
高級ブランド「常磐もの」の食味豊かな貝
福島県から茨城県にかけての沿岸海域は、親潮(寒流)と黒潮(暖流)がぶつかる海の境「潮目」。潮目の海には、黒潮とともに北上してきた小魚が親潮で発生するプランクトンを目当てに集まり、さらにそれらの小魚を餌にする大型魚も集まります。このように非常に恵まれた漁場のため、四季折々に魚種が豊富で身が引き締まっており、もちろん味も良いことから、東京の旧築地市場でも「常磐もの」と呼ばれて高値が付けられてきました。
そんな「常磐もの」の中には貝類も多く、6月からはホッキ貝の漁が始まります。
ホッキ貝はバカガイ科に属する2枚貝で、正式名称は「ウバガイ(姥貝)」です。よく知られるホッキ貝という名前は、アイヌ語でホッキ貝を意味する「ポキセイ」という言葉が語源だという説も。また東北から北海道沿岸にかけて多く分布していることから、「北寄貝」という漢字があてられたようです。
常磐沖はホッキ貝漁の南限。特に相双沖では明治時代からホッキ漁が盛んでした。相双沖のホッキ貝は漁獲量が多く、また身の大きさや甘みの強さなどが特長で、地元の食材として長く親しまれています。コキコキした弾力のある食感も絶品!
ホッキと言えば、白い身で先の方が赤い貝というイメージが強いかもしれません。でも生のホッキ貝は、先の方が薄い青紫色。加熱することで赤い色に変わります。常磐もののホッキ貝はきれいなピンク色に変色しますが、これは身が柔らかい証なのだとか。
栄養成分としては、旨み成分のアラニン・グリシンといったアミノ酸が多く、動脈硬化予防や疲労回復を助けるタウリン、さらにカルシウム・マグネシウム・鉄分などのミネラルも豊富。造血作用や神経痛の改善に良いとされるビタミンB12も含まれます。
身の柔らかさを堪能できる「ホッキ飯」
刺身や天ぷらをはじめ様々な食べ方がありますが、相双地区でおなじみなのは「ホッキ飯」。飲食店はもちろん、各家庭でもよく食べられている郷土料理です。美味しく仕上げるコツは、ご飯とホッキを一緒に炊きこまないこと。ホッキはサッと湯がくか、醤油やみりんなどで煮込んでおき、炊きあがったご飯に混ぜ合わせることで身の柔らかさを堪能できます。
なお、活ホッキ貝は相馬双葉漁業協同組合の「磯部水産加工施設直売所」や、復興市民市場「浜の駅 松川浦」などで購入できるので、自宅でいろいろな調理に挑戦してみてはいかがでしょう。
最期にオマケで、「ウニの貝焼き」のお話を。貝の殻にウニを「これでもか!」とふんだんに盛って蒸し焼きにした、いわき市の郷土料理です。この貝焼きに使われているのが、ホッキ貝の殻。三角と丸の中間のような形状で厚みも硬さもあるので、あんなにもウニを山盛りにできるのですね。
ふくしま常磐ものNAVI
https://fukushima-jobanmono.jp/enjoy/know/topic134/
磯部水産加工施設
https://soso-gyokyo.jp/isobe
浜の駅 松川浦
https://www.hamanoeki.com/
最後に、当社では下記の検査を行っておりますので、何なりとご用命ください。
● 食品、土壌、水などに含まれる放射能濃度を測定する放射能検査
詳しくはこちらから