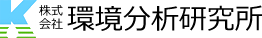ふくしま食紀行
ふくしま食紀行(その7)…そば
色・味・香りが最も優れている新そば
いよいよ新そばの季節がやってきました。最近では品種改良や栽培形態の変化が進み、春や夏に味わう新そばも注目されていますが、「新そばと言えば秋」という方も多いのではないでしょうか。
いずれにしても“新そば”とは、収穫から1~2か月程度で提供されるもの。いわば期間限定のごちそうなのです。そばは風味や味の劣化が早い農産物。保存設備が発達したことでいつでも美味しいそばが食べられるようになりましたが、やはりそば本来の色・味・香りを堪能するのなら、収穫したての新そばは見逃せません。
そばはヘルシーフードとしても知られており、「そば好きは健康で長寿だ」と言われています。その理由は豊富な栄養素。特に、ポリフェノールの一種である「ルチン」が多く、ビタミンCと一緒に働いて血圧を下げたり、毛細血管を強くしたりする働きもあります。
また穀類の中でもたんぱく質を多く含んでおり、必須アミノ酸もバランスよく含まれているため筋肉や皮膚に使われやすいと言われています。
食物繊維やビタミンB群、カリウム、マグネシウム、リンなどのミネラルも豊富。ただしそばの栄養成分の多くは水溶性なので、茹で汁である“そば湯”もぜひいただきましょう。
どんなそばが好き?食べ比べて出合いたい
種まきから2か月ほどで収穫できるそばは、朝晩の寒暖差が大きく冷涼な地が栽培に適していると言われます。確かに全国的に見ても「そばの産地」と謳われるのは、北海道・東北・信州などが多いですね。
福島県も古くから在来種のそば栽培が盛んにおこなわれてきました。栽培面積・生産量とも多く、令和4年産の作付面積は全国第5位となっています。
福島県内のそば処の筆頭は、県内の作付面積の約8割を占める会津地方。そばにまつわる会津の豆知識をいくつかご紹介しましょう。
●猪苗代湖畔の「惣座(そうざ)遺跡」から出土したそばの実は、平安時代から鎌倉時代にかけて栽培されたものと判明しており、福島県におけるそば文化の歴史の長さを物語っています。
●初代会津藩主となった保科正之公はそばを非常に好んでおり、幼少期から過ごした信州高遠(たかとお)のそばの文化を会津に伝えました。つゆに辛味大根の汁を使う「高遠そば」は会津で受け継がれ、その発祥地である高遠町(長野県伊那市)との親善交流に一役買っています。
●昭和50年代からそばで町おこしをしてきた「山都そば(喜多方市山都町)」は、世代を超えて地域に受け継がれてきた食文化であることが文化庁に認められ、今年3月に「100年フード(令和4年度)」に認定されました。
●平成19(2007)年には、下郷在来を原種とする「会津のかおり」という品種が福島県のオリジナルブランドとして新たに登録されました。
会津地方以外にもそば処は県内各地にあります。
県南では、「寛政の改革」で知られる松平定信公が冷害に強いそばの栽培を推奨。以来、「白河そば」として、みちのくの玄関口で旅人をもてなす郷土の味になりました。
奥羽山脈や阿武隈高地といった比較的標高の高い地域でも栽培されています。2021年夏に復興事業「東北復興宇宙ミッション」で宇宙に打ち上げられた「山木屋在来そば(川俣町山木屋地区)」は、昨年10月に「高原の宇宙(そら)」として商標登録されました。
そばは栽培エリアや店舗によって、それぞれのこだわりがあります。また食べる方にとっても「十割そばを味わいたい」「やっぱり田舎そばが好き」「あったかいそばが最高」など好みは十人十色。あれこれ味わってみて、ぜひご自身のお好みを探してみてはいかがでしょう。
ちなみにこの時期は、県内各地で新そば祭りが開催されます。
はしごして楽しむのもおすすめですよ。
ぜひ「福島県 新そばまつり」で検索してみてください。

最後に、当社では下記の検査を行っておりますので、何なりとご用命ください。
● 食品、土壌、水などに含まれる放射能濃度を測定する放射能検査
詳しくはこちらから