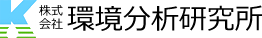ふくしま食紀行
ふくしま食紀行(その11)…ふくしまの鶏
ふくしま三大ブランド鶏「会津地鶏」「川俣シャモ」「伊達鶏」
今回は、福島県が誇る鶏「会津地鶏」「川俣シャモ」「伊達鶏」をご紹介しましょう。この3種は「ふくしま三大ブランド鶏」として推進協議会を立ち上げており、県内外に広くその品質や味の良さをアピールしています。
「会津地鶏」には400年以上の歴史があります。もともとは観賞用に飼われていたと言われており、外見の特徴である黒々とした長い尾羽は、郷土芸能「会津彼岸獅子」の獅子頭の装飾にも使われていました。絶滅寸前でしたが、昭和62(1987)年に当時の福島養鶏試験場が調査したところ、完全な会津の固有種と判明。その後、原種の増殖・維持・改良を重ねた結果、適度な歯ごたえのある肉質、噛みしめるほど深まるコクと旨みを兼ね備えた会津地鶏が生まれました。焼き鳥、鍋、唐揚げなどにぴったりです。
「川俣シャモ」は、町の機屋(はたや)の旦那衆が江戸時代頃に娯楽として飼い始め、闘鶏を楽しんだことが始まりと言われています。やがて昭和の後期、町おこしの特産品として注目され、昭和60(1985)年に川俣シャモが誕生。さらに町ぐるみでブランド化が進められ、品質改良によって肉質が向上しました。適度な弾力のある肉質や、噛めば噛むほど広がる鶏本来の旨みが特徴です。2022年3月には、農水省のGI(※1)に登録されました。鍋物を始め、ラーメン、丸焼き、親子丼などにもおすすめです。
「伊達鶏」は1985年に飼育が始まった銘柄鶏。その当時の鶏肉は、肉質が柔らかい「ブロイラー」もしくは歯ごたえのある「地鶏」が主流でした。そこで伊達物産(伊達市)が、料理人の求める“調理がしやすく、料理して美味しい”鶏肉の開発に取り組んだのです。「南東北の気候風土に合った美味しい鶏を育てる」という目標のもと、熱心な試行錯誤によって美味しい伊達鶏の開発に成功。広い開放鶏舎で存分に動き回る伊達鶏は、余計な脂身がなく、肉質は柔らかくて非常にジューシー。唐揚げや炒め物などに最適です。
地域名が付いていれば全部「地鶏」?いいえ、違います。
現在、日本国内で流通している鶏肉はおもに3種類。「地鶏」と「銘柄鶏」と「ブロイラー」です。どれも聞いたことがある名称だと思いますが、明確な違いをご存じでしょうか。
まず「ブロイラー」は、スーパーなどで見かける「若鶏」のこと。ふ化から50日ほどで出荷される若鶏で、早く大きく育てられます。大量生産が可能なため、日本国内で流通している国産鶏肉の90%以上を占めています。
「銘柄鶏」は、飼料や育て方に工夫を加えて肉質や味を改良した鶏。JAS(日本農林規格)による定義はありませんが、日本食鳥協会で銘柄鶏のガイドラインを設定しています。銘柄鶏は、一般的なブロイラーと同種類の「若鶏系」と、希少な赤鶏を両親に持つ「赤系」の2つに分類されています。赤系の銘柄鶏は、国内流通の約2%。「伊達鶏」は、赤系の銘柄鶏です。
「地鶏」には、JASによる定義があります。まずは、在来種(※2)の鶏の血が半分以上入っていること。さらに「①ふ化日から75日以上 ②28日齢以降は平飼い ③28日齢以降は1平方メートルあたり10羽以下の密度」という3つの飼育条件をクリアしなければなりません。単にその土地の名前が付いているから「地鶏」ではないのです。「会津地鶏」と「川俣シャモ」はJASに則った「地鶏」です。ちなみに地鶏は、国内流通全体のわずか1%。
つまり「会津地鶏」「川俣シャモ」「伊達鶏」は、いずれも希少なブランド鶏。美味しさや肉質は言わずもがな!県内はもちろん、首都圏や関西などにもこれらの鶏を取り入れている飲食店が数多くあります。
肉そのものだけでなく、とりめしの素、スープ、鍋セット、カレーなどの加工品も販売されているので、ぜひ味わってみてはいかがでしょう。
(※1)GI…地理的表示保護制度/その地域ならではの産品の名称を、地域の知的財産として保護する制度
(※2) 在来種…明治時代までに日本に導入され定着した約38種の鶏
ふくしま三大ブランド鶏推進協議会
https://3dori-fukushima.com/
日本食鳥協会
https://www.j-chicken.jp/
日本赤鶏協会
https://nippon-akadori.or.jp/

赤坂盆踊り会場での三大鶏焼き鳥販売
最後に、当社では下記の検査を行っておりますので、何なりとご用命ください。
● 食品、土壌、水などに含まれる放射能濃度を測定する放射能検査
詳しくはこちらから