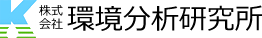職人の手仕事~伝統工芸
職人の手仕事~伝統工芸(その3)…土湯こけし
遠刈田、鳴子と並ぶ「三大こけし」の一つ
江戸時代に、東北地方の温泉地のお土産として作られ始めたという工芸品「こけし」。それらは「伝統こけし」と呼ばれており、産地ごとに個性的な特徴を持つ12系統に分類されています。その1つが「土湯系」。福島市の土湯温泉で作られており、宮城県の遠刈田・鳴子と並んで「三大こけし」の一つに挙げられています。
土湯こけしは、頭が小さなたまご型で胴体は細身。頭頂部には黒い輪(蛇の目)が、前髪の両脇には赤い髪飾り(カセ)が描かれています。さらに、切れ長のくじら目、たれさがった丸い鼻、おちょぼ口という表情が、何とも言えない愛らしさ。頭を胴にはめ込む「はめ込み式」のこけしで、首を回すとキイキイと温かみのある音が出ます。
土湯こけしは、もともと土湯温泉で木の器などを作っていた職人たちの手仕事として生まれました。ロクロでお椀やお盆などを作る職人を木地師と呼びますが、木地の技術が土湯に伝わった経緯には諸説あります。
①戦国時代、蒲生氏郷が会津転封の際に、近江から職人を連れてきた。
②江戸初期、会津藩祖・保科正之が信州高遠から木地屋を連れてきた。
③もっと古い時代に会津の木地屋から高森部落に伝えられた。
いずれにしても会津から土湯に木地の技術が伝わり、それがこけし作りへつながったと考えられます。それが長きにわたって受け継がれ、現在もこけし工人たちが一体一体丁寧にぬくもりあふれる土湯こけしを手がけています。
こけしの絵付け体験やこけし祭りにも注目
温泉街入口にある「土湯温泉観光交流センター【湯愛舞台(ゆめぶたい)】」には、土湯こけしを始め東北6県のこけし約2000体が展示されています。無料で見学可能。ずらりと並んだこけしは実に壮観!それぞれの特徴を見比べてみるのも楽しそうですね。
湯愛舞台では、こけしの絵付け体験(970円)も可能。予約不要で気軽に体験できるので、世界に一つだけのマイこけしを描いてみてはいかがでしょう。
なお毎年6月初めの土日には、「こけし祭り」を開催。土湯系工人および招待工人のこけし販売や、絵付けコンテスト、トークショーなど内容盛りだくさんです。
●土湯温泉観光協会
024-595-2217
https://www.tcy.jp/
最後に、当社では下記の検査を行っておりますので、何なりとご用命ください。
● 食品、土壌、水などに含まれる放射能濃度を測定する放射能検査
詳しくはこちらから