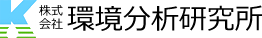職人の手仕事~伝統工芸
職人の手仕事~伝統工芸(その5)…焼物
400年の歴史を誇る東北最古の焼き物【会津本郷焼】
福島県では、2つの陶磁器が国の伝統工芸品に指定されています。まず1つめが、約400年続く「会津本郷焼」。会津に入封した蒲生氏郷(がもううじさと)が、文禄2(1593)年のお城の大改修の際に屋根を瓦葺きにするため、播磨(兵庫県)から瓦工を招いて瓦を作らせたことに始まると言われています。
さらに正保2(1645)年には会津藩祖・保科正之が、尾張・瀬戸(愛知県)生まれの陶工を召し抱え、陶器の製造が始まりました。その後、江戸時代の寛政12(1800)年には白磁の製法も開発され、現在、関東以北で陶器と磁器の両方を作る唯一の産地となっています。幕末の会津戦争では作陶も大きな打撃を受けましたが、その後復興し、明治時代には陶磁器業関係者が1000名を超えるなど、会津本郷焼は隆盛を極めました。
素朴でのびやかな造形美と使い勝手の良さで知られる陶器。純白の美しい肌と優雅な文様や色彩が魅力の磁器。会津本郷焼はそれぞれの技術や伝統を受け継ぎつつ、現在は13の窯元が独自の個性や作風を追求しながら、日々新たな創造へ取り組んでいます。
毎年8月の第一日曜日には、「会津本郷せと市」を開催。会津本郷焼の窯元はもちろん、全国各地の窯元の露天も並び、“掘り出し物”を求める多くの人でにぎわいます。
◆会津本郷焼事業協同組合
https://aizuhongouyaki.jp/
「青ひび、走り駒、二重焼き」が独特な【大堀相馬焼】
もう1つ国指定を受けている「大堀相馬焼」は、双葉郡浪江町の大堀地区で作られてきました。江戸時代の元禄年間、相馬中村藩士の半谷休閑(はんがい きゅうかん)が、地元で採れる陶土を使って下僕の佐馬(さま)に茶碗などを作らせ、駒絵を描いて売り出したのが始まりと言われています。
同じ相馬藩のもとで作られた「相馬駒焼」が主に藩主・相馬氏への献上品であったことに対し、大堀相馬焼は庶民の日用雑器として広く親しまれました。その後、相馬藩が陶器を特産品として保護し、技術者の養成や生産向上が進みます。江戸時代末期には、窯元数が100戸を超えるほど作陶が盛んにおこなわれていました。明治の廃藩置県によって藩からの援助が途絶えた後、窯元数が激減しましたが、徐々に再興していき、明治から大正時代にかけて大堀相馬焼ならではの独特な特徴が花開いていきました。
大堀相馬焼の特徴は、まず器全体に広がっている「青ひび」。これは江戸末期に誕生した青磁釉によるもので、素材と釉薬との収縮率の違いから生じる貫入(ひび模様)です。このひびが入る時に発生する“ぴーん”という繊細な貫入音は、「うつくしまの音 30景」にも選ばれています。
さらに「走り駒」が描かれていることも、特徴の1つ。狩野派の筆法によって相馬藩の御神馬を描いており、縁起物として重宝されてきました。そして最も代表的な特徴と言える「二重焼き」の技法。器の構造が二重になっており、入れたお湯が冷めにくく、それでいて熱いお湯を入れても持ちやすいという優れものです。
2011年3月11日、東日本大震災による原発事故の影響で、震災前に20軒以上あった窯元も町外への避難を余儀なくされました。大堀相馬協同組合は二本松市内に仮設工房兼事務所を開設していましたが、2021年に浪江町内に完成した「なみえの技・なりわい館(道の駅なみえ内)」で新たに工房・ギャラリー・事務所を開設。陶芸体験なども実施しています。また、多くの窯元たちは福島県内外各地で窯を再開しており、大堀相馬焼は新たな息吹とともに「福島の焼き物」として広く知られるようになっています。
◆大堀相馬焼協同組合
http://www.somayaki.or.jp/

最後に、当社では下記の検査を行っておりますので、何なりとご用命ください。
● 食品、土壌、水などに含まれる放射能濃度を測定する放射能検査
詳しくはこちらから