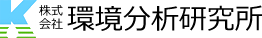職人の手仕事~伝統工芸
職人の手仕事~伝統工芸(その6)…会津塗
室町時代から始まった日本三大漆器の一つ
山中塗・輪島塗(石川県)や、紀州塗(和歌山県)と並んで、日本三大漆器の一つに挙げられる「会津塗」。その発祥はなんと室町時代で、当時会津を治めていた芦名氏が、漆の木の植樹を奨励したことに始まると伝わっています。
やがて天正18(1590)年、会津に入封した蒲生氏郷が故郷・日野(滋賀県)から木地師や塗師などの職人を呼び寄せたことから最先端の技術がもたらされ、会津塗は産業として大きく発展していきました。江戸時代には会津藩祖・保科正之を始め歴代藩主によって保護奨励され、ますます隆盛を極めます。その頃は全国でも注目される漆器となり、大衆に漆器文化を根付かせることなりました。
やがて幕末になると外国への輸出もされるほど一大産地として名を馳せました。戊辰戦争では壊滅的な打撃を受けましたが、大店の商人たちによって職人が呼び戻され徐々に復興。大量生産のための独自技術の開発、完全分業制による生産システムの構築などから隆盛を取り戻します。さらに焼金蒔絵が開発されたことで、高級漆器としての地位を確立していきました。
工程や作る物ごとに専門職人がいる分業生産
会津塗の製造には「木地」「塗」「加飾」と呼ばれる三部門があり、それぞれに専門の職人がいます。さらに木地師なら、椀などの「丸物」を作る人は「丸物師」、重箱などの板物を作る人は「板物師 (もしくは会津ならではの呼び方で『惣輪師』」) 」と細分化。それぞれ製造工程が異なるため、塗師も「丸物塗師」と「板物塗師」の専門職に分かれています。
会津塗の特徴は、縁起の良い意匠や加飾の多彩さ。同じ「会津塗」でも、バリエーション豊富なデザインを楽しむことが出ます。例えば、彩り豊かな漆絵の具で塗物に縁起のいいモチーフを描く「漆絵」、漆を塗った面を彫り出して溝に金箔や消金粉を蒔きつける「沈金」、漆で絵を描いて金粉や色粉を蒔きつける「蒔絵」、貝殻を貼り付ける「螺鈿」など様々な装飾技法があり、独特の美しさや豊かな表情が何とも言えません。それらは職人の手仕事である一方、“芸術品”と呼ぶべき美しさを放っています。
会津塗は、昭和50(1975)年、全国で2番目に国の伝統的工芸品の指定を受け、今年3月には福島県の重要無形文化財に指定されました。
現在は椀や重箱といった伝統的な漆器に加えて、時代のニーズにも柔軟に対応。アクセサリーやインテリア、スマホケースなど、身近な日用品も数多く生み出されています。器以外にも長く愛用できるお気に入りの「会津塗」を見つけてみてはいかがでしょう。
◆会津漆器協同組合
http://www.chuokai-fukushima.or.jp/aizushikkikumiai/index.html

最後に、当社では下記の検査を行っておりますので、何なりとご用命ください。
● 食品、土壌、水などに含まれる放射能濃度を測定する放射能検査
詳しくはこちらから