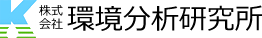職人の手仕事~伝統工芸
職人の手仕事~伝統工芸(その7)…蝋燭(ろうそく)
県指定の伝統的工芸品、会津地方の2つの蝋燭
会津地方には、県の伝統的工芸品に指定されている蝋燭(ろうそく)が2つあります。
1つは1997年に指定された「会津絵蝋燭(会津若松市)」。もう1つが2005年に指定された「金山漆ろうそく(金山町)」です。
今から約600年前の室町時代、会津を治めていた芦名盛信によって漆樹の栽培が奨励されました。それによって、漆の実から採取される蝋を利用した蝋燭作りが始まったと言われています。蝋燭は会津の特産品として広まり、織田信長への贈答品としても用いられました。
真っ白な蝋燭に職人が咲かせる色とりどりの花
やがて戦国時代の天正年間、会津の地に移った蒲生氏郷が近江から職人を呼び寄せ、より品質が向上していきます。さらに牡丹や藤、菊といった季節の花の絵が描かれるようになり、「会津絵蝋燭」は高級工芸品・美術品として、おもに武家や公家、神社仏閣といった上流社会で珍重されるようになりました。
他人の結婚式をお祝いする時に使う「華燭の典(かしょくのてん)」という言葉がありますが、「華燭」は祝いの席などに用いられる華やかな灯火を意味するもので、日本においては結婚式に一対の絵蝋燭を灯したことから「華燭の典」という呼び方をするようになったのだとか。
会津絵蝋燭は江戸時代になっても幕府への献上品や他藩への贈答品として使われ、明治以降は庶民にも広がりを見せました。雪国・会津では花の咲かない冬の時期に、花に代わって絵蝋燭を仏壇に飾るようになったのだとも言われます。
現在はハゼの実から採った蝋を使っていますが、一本一本手作り・手描きされ、年代を問わずインテリア雑貨やお土産品としても愛されています。会津若松市内には蝋燭の絵付け体験ができる工房があるので、オリジナルの蝋燭を作ってみませんか。
◆絵付け体験ができる工房◆
山形屋本店
https://rousoku.com/
小澤ろうそく店
https://www.aizuerousoku.com/
ほしばん絵ろうそく店
https://hoshiban.com/
途絶えた漆蝋が復活!国内唯一の希少な蝋燭
植物から採取した蝋を原料とするものを「和蝋燭(わろうそく)」と呼びます。江戸時代に会津藩は漆蝋(うるしろう)作りを奨励しており、会津の漆蝋は江戸で消費される和蝋燭の3分の2を占めるほどに発展していました。
やがて漆蝋の生産は途絶えてしまいましたが、2001年に奥会津の金山町で町内の有志による「和ろうそく復古会」というグループが結成され、昔ながらの漆蝋燭作りに挑むことになります。復古会のメンバーは道具類を収集・復元し、昔を知る人の記憶を頼りに試行錯誤を繰り返しました。そして4年後、伝統的技法を活かした「金山漆ろうそく」が再興。金山町の漆畑で栽培した漆の実で蝋を採り、イグサを芯にして何度も蝋を掛け、太くなった漆蝋をカンナで蝋燭の形に整えています。
その素朴な風合いには、見ているだけで心をホッと温めてくれるような懐かしさが。ただし漆から採れる蝋が非常に少なく、また手間もかかることから、なかなか大々的に販売するまでには至っていません。しかし国内唯一の「漆蝋」という希少な灯を再び途絶えさせないよう、金山町や復古会のメンバーが日々奮闘しているので、新たな情報に期待がかかります。
ちなみに金山町の「生活体験館」では、漆ではなく蜜蝋を使った蝋燭の絵付け体験ができるので、奥会津の旅の思い出として楽しんでみてはいかがでしょう。
◆金山町生活体験館
https://www.do-fukushima.or.jp/shoukoukai/kaneyama/html/kankou/seikatut.html

最後に、当社では下記の検査を行っておりますので、何なりとご用命ください。
● 食品、土壌、水などに含まれる放射能濃度を測定する放射能検査
詳しくはこちらから