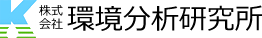職人の手仕事~伝統工芸
職人の手仕事~伝統工芸(その9)…奥会津編み組細工
歴史をさかのぼれば、始まりは縄文時代!
ヒロロ(ミヤマカンスゲ)、山ブドウ、マタタビなどの素材を使って製作される「奥会津編み組細工」。三島町を主な産地としており、積雪期の手仕事として日々の生活に使うカゴやザルなどが作られてきました。地域の人々が一つ一つ丁寧に手がけており、何とも言えない素朴な風合いと日常使いにぴったりの丈夫な作りが大きな特徴です。
その歴史は驚くなかれ、縄文時代までさかのぼるのだとか。三島町にある縄文晩期(約2,400年前)の「荒屋敷遺跡」からは、縄や編み組といった遺物が数多く出土しました。それらの技法は暮らしの中で伝承され、今に至っています。つまり現在ある編み組細工は、自然の素材を使って自ら民具を生み出すという、縄文から受け継がれてきた文化であり、時代を越えてなお息づいている生活の知恵と言えるでしょう。
2003年に国の伝統工芸品に指定された奥会津編み組細工。現代のライフスタイルやニーズに合ったデザインを取り入れ、より注目度が高まっています。手さげかご、ショルダーバッグ、長財布など、製品ラインナップも充実。町の施設である「生活工芸館」で展示販売をおこなっているので、機会があればぜひ、その精緻な技術を手に取ってみてはいかがでしょう。
三島町生活工芸アカデミーの8期生を募集中
なお三島町では、生活に必要な道具を自ら作り出す“ものづくり精神”を後世に伝えていこうと「生活工芸運動」を展開しています。2017年度からは、後継者不足を解消し、ものづくり精神や様々な技術を伝承していくため、「生活工芸アカデミー」を開講。三島町で暮らしながら、町の様々な担い手となる人材を育成しています。
その第8期生を、2024年12月26日まで募集中。集落での共同生活の中で、農作業や地区行事を体験したり、奥会津編み組細工の実技を学んだりできる貴重な機会です。そして縄文から続く編み組細工の技術を、後世に橋渡しする役目も担うことになるでしょう。興味のある方は、生活工芸館で詳細を尋ねてみてください。
◆生活工芸館◆
https://www.okuaizu-amikumi.jp/

最後に、当社では下記の検査を行っておりますので、何なりとご用命ください。
● 食品、土壌、水などに含まれる放射能濃度を測定する放射能検査
詳しくはこちらから