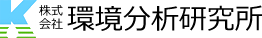職人の手仕事~伝統工芸
職人の手仕事~伝統工芸(その10)…手漉き和紙
長く受け継がれる丈夫で美しい和紙
職人が一枚一枚丁寧に仕上げる「手漉き和紙」。原料となる楮(こうぞ)の刈り取りや繊維を採るための皮剥き、冷たい水の中でおこなう漉きの工程など、完成までに手間と労力がかかる工芸品です。それゆえに手漉きの和紙は強靭で独特の風合いを持っており、非常に貴重な和紙と言えるでしょう。
福島県内でも、古くから手漉きの和紙がいくつか作られています。その中から、今回は県の伝統工芸品に指定されている2つの手漉き和紙をご紹介しましょう。
1つは二本松市の「上川崎和紙」。もう1つは郡山市の「海老根伝統手漉和紙」です。
平安貴族にも珍重された「上川崎和紙」
二本松市の上川崎地区では、1,000年以上も前、平安時代から手漉き和紙が作られてきました。当時は紙が大変貴重だった時代。「みちのく紙」と称され、平安貴族に珍重されていたようです。紫式部や清少納言が好んだ「まゆみがみ」も、この地で漉かれたのではないかと言われています。
江戸時代には二本松藩が紙漉きを奨励し、盛んに作られていました。しかし近代になって西洋から機械漉き技術が導入され、印刷物が普及するにつれて、いわゆる“洋紙”が普及。上川崎和紙は、徐々に生産量が減少していったようです。その後1991年に「上川崎和紙振興組合」がつくられ、1993年に県指定の伝統的工芸品に認定されました。
現在は、道の駅「安達」に併設する「二本松市和紙伝承館」で、手漉き和紙の保存や技術継承がおこなわれています。なお1995年に開催された「ふくしま国体」の表彰状には、この上川崎和紙が使われました。さらに市内の多くの小中学校では、児童・生徒が自ら漉いた和紙が卒業証書に用いられています。
また和紙伝承館では、和紙で作ったランプや耳かきといった多彩な和雑貨も販売されています。館内に工房があり、手漉き体験・工芸品体験(内容によって要予約)もできるので、気軽に立ち寄ってみてはいかがでしょう。
◆二本松和紙伝承館(道の駅「安達」上り線内)◆
https://www.michinoeki-adachi.jp/shop_nobori/washi.html

一度途絶えた技術が復活「海老根伝統手漉和紙」
郡山市中田町の海老根地区では、1658年頃から和紙の手漉きが始まったと言われています。阿武隈山系には和紙の原料である楮が豊富にあり、きれいな湧き水にも恵まれていたことから、農家の冬の副業として発展しました。江戸時代末期から明治時代にかけての最盛期には地区の80戸が和紙作りに従事していたようです。しかし昭和40年代には10数戸のみに減少。平成に入る頃、この地区での手漉き和紙生産は途絶えてしまいました。
その後、1998年には地元の人々によって「海老根伝統手漉和紙保存会」が結成され、再び和紙作りが始まります。地元の人々の熱意で復活した海老根伝統手漉和紙は、2003年に県の伝統的工芸品に指定されました。海老根の和紙は黄色みがかった色から、時が経つにつれて白くなっていきます。無添加ならではの特徴であり、生きている紙「生紙(きがみ)」と呼ばれているのだとか。
昔は障子紙として使われることが多かったそうですが、現在は毎年9月に地区で開催される祭り「海老根秋蛍」の灯篭や、地元の小中学生の卒業証書などにも用いられています。和紙は工房で直売している他、受注製造販売にも対応してくれるとのこと。寒い時期には手漉き体験もおこなわれているので、まずはお問い合わせを。
◆海老根伝統手漉和紙保存会事務局◆
024-943-4264
最後に、当社では下記の検査を行っておりますので、何なりとご用命ください。
● 食品、土壌、水などに含まれる放射能濃度を測定する放射能検査
詳しくはこちらから