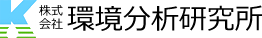疏水百選
水を引くために、人工的に造られた水路のうち、船舶の移動を目的とするものを「運河」、灌漑や水道、工業に用いることを目的とするものを「用水路」といいますが、疏水は、これらの機能を併せ持つものです。
疏水百選は、日本の農業を支えてきた代表的な疏水を選定して、疏水がもたらす“水・土・里”(みどり)を次世代に伝え、維持する活動として、全国水土里ネット(全国土地改良事業団体連合会)企画研究部が、選定したものです。「農業・地域復興」「歴史・伝統・文化」「環境・景観 」「地域コミュニティの形成」の4項目の視点を基準として、国民による投票を受け付け、平成18(2006)年に、全国の疏水の中から110箇所を選びました。
福島県内では、安積疏水(郡山市)と会津大川用水(会津美里町、会津若松市)の2箇所が選ばれました。


安積疎水は、郡山発展の礎となった水路です。猪苗代湖より取水し、郡山市とその周辺地域の安積原野に農業用水・工業用水・飲用水を供給し、水力発電にも使用されています。
開削は、国直轄の農業水利事業の第一号として、明治12(1879)年から始まり、3年の年月と、延べ85万人の労働力、総経費40万7千円(現在の価値で約400億円)をかけて、明治15年に完成しました。
那須疏水(栃木県)、琵琶湖疏水(滋賀県、京都府)と並ぶ日本三大疏水の一つです。また、関連する施設は、「甦る水100選(せせらぎこみち)」、「水の郷百選(水と緑がきらめく未来都市 郡山)」、「近代水道百選(豊田浄水場)」など、さまざまな水をめぐる百選に選定されています。
会津大川用水は、大川ダム(会津若松市と南会津郡下郷町にまたがる阿賀川の上流部)を水源として、会津美里町本郷地区と会津若松市北会津町の一部などに農業用水と生活用水を供給し、発電にも利用されています。
昭和54(1979)年から平成6(1994)年にかけて、国営かんがい排水事業として、用水に水を引き込む施設や水路などの整備が進められました。
本郷地区には、会津本郷焼の窯元がかつて原料の石を砕くために使っていた水車がありましたが、大正時代に、石を粉砕する機械が導入されてから姿を消しました。用水路が整備された現在では、町並環境整備事業の一環で水車を再現した公園などが設置されて住民の憩いの場として親しまれています。
最後に、当社では下記の検査を行っておりますので、何なりとご用命ください。
●食品、土壌、水などに含まれる放射能濃度を測定する放射能検査 詳しくはこちらから