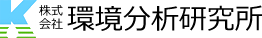温泉(三○○)
温泉あれこれ(その6)…温泉の三○○について
温泉にまつわる“三くくり”あれこれ
三古泉・三美人湯・三大こけし
今回は、温泉の「三○○」をご紹介しましょう。
まずは、「日本三古泉(古湯)」。日本で古くから知られている歴史的な三カ所の温泉です。これには2つの説があり、1つめが『日本書紀』や『風土記』の記述による「道後温泉(愛媛県)」「有馬温泉(兵庫県)」「白浜温泉(和歌山県)」。もう1つの説として、『延喜式神名帳』に基づく三古泉の中には、「道後温泉」「有馬温泉」と並んでいわき市の「いわき湯本温泉」が挙げられています。
『延喜式神名帳』とは、平安時代の法制書『延喜式』の巻九・巻十のこと。全国の神社が紹介されており、その中で「陸奥国磐城郡小七座・ 温泉(ゆ)神社」と記されています。ただし、いわき湯本温泉の開湯はもっと古く、奈良時代にまでさかのぼるのだとか。
続いては、いわき~新潟にかけて横断する「磐越三美人湯」に注目を。
その三美人湯とは、「いわき湯本温泉(含硫黄-ナトリウム-塩化物・硫酸塩温泉)」、郡山市の「磐梯熱海温泉(アルカリ性単純温泉)」、新潟県の「月岡温泉(含硫黄―ナトリウム―塩化物泉)」。硫黄成分を豊富に含むお湯や、pH値7.5以上のアルカリ性のお湯は、お肌がつるつるになる“美人の湯”。磐梯熱海温泉には「都から来た美しい姫君の難病を治癒した」という伝説もあり、それが美人の湯としての評判を高めているのかもしれませんね。
最後は、温泉土産の代表格・こけし。現在、こけしの種類は12系統に分類されますが、すべてが東北産。産地によって形や模様に特徴があり、それぞれに熱いファンが付いています。その中で「三大こけし発祥地」と言われるのが、「鳴子系(宮城県)」「遠刈田系(宮城県)」「土湯系(福島市)」。
土湯こけしは、頭頂部の蛇の目模様、赤い髪飾り「カセ」、クジラ目、たれ鼻、おちょぼ口などの特徴があり、素朴で愛らしい風貌が人気を呼んでいます。土湯こけしの始まりは江戸時代後期ですが、木地職人の技術がこの地に伝わったのはもっと以前、一説には安土桃山時代とも言われています。
日本や世界には、“三くくり”のあれこれがたくさんありますが、身近な場所や物がその一つに挙げられていると、誇らしい気持ちになりますね。温泉関連以外でも、そんな「わが町自慢」をぜひ探してみませんか。

最後に、当社では下記の検査を行っておりますので、何なりとご用命ください。
●食品、土壌、水などに含まれる放射能濃度を測定する放射能検査
詳しくはこちらから